──「競争」か「共創」か、自分の価値観で選ぶ時代へ
はじめに:物価が上がるだけじゃないインフレの本質
「なんだか最近、物価が高くなってるよね」
そんな会話が当たり前になって久しいこの頃。実はインフレ(=物価上昇)は、単に生活費がかさむというだけでなく、私たちの「働き方」や「社会の構造」そのものに深い影響を及ぼしつつあります。特に20代の若手社会人にとっては、今後のキャリアや生き方を考える上で、インフレ時代の“企業依存リスク”をしっかり理解しておく必要があります。
本コラムでは、以下の視点からインフレと企業依存のリスクをひも解き、私たち若い世代がどんな選択肢を持つべきかを一緒に考えていきましょう。
1. 世界経済の停滞とダイナミズムの喪失
2000年代のグローバル経済は、ITと物流革命のダイナミズムに満ちあふれていました。新興国の台頭、越境取引の自由化、デジタル化による新ビジネスの誕生。だれもが「世界は広がっていく」と信じて疑わなかった時代です。
しかし、2020年代に入ると様相が一変。コロナ禍、米中対立、ウクライナ戦争、サプライチェーンの混乱。これらが引き金となり、世界は「分断」や「内向き志向」に傾いていきました。
その結果、グローバル経済の持っていた“拡張性”という魅力が弱まり、企業が「リスクを取って成長を目指す」よりも「足元を固めて守りに入る」方向へと動いています。この変化は、若手社員にとってのチャレンジ機会の減少や、キャリアの流動性を鈍化させる要因になっています。
2. 輸出頼みの日本経済の停滞
日本経済は長らく「モノを作って海外に売る」モデルに支えられてきました。自動車、機械、電子部品など、世界的に競争力のある製造業が経済の屋台骨を担ってきました。
しかし近年は、円安による一時的な利益増を除けば、製造拠点の海外移転や新興国の追い上げ、グローバルな需要の鈍化などにより、輸出頼みの構造に陰りが見えています。
内需はといえば、高齢化による消費の鈍化と人口減少。個人消費が伸び悩むなかで、若い世代が自分の働きに見合う報酬を得るのは、年々難しくなっています。
3. 企業競争力の差が生む給与格差の拡大
経済が拡張しづらくなった環境下では、「勝てる企業」と「勝てない企業」の差がより顕著になります。
一部のグローバル企業やIT系、医薬・金融などは利益を上げて給与水準も上昇傾向にありますが、大多数の中小企業や国内志向の業界では、インフレに見合った賃上げはできていません。
こうした格差は、同じ能力や努力を持っていても、「どの企業にいるか」によって年収が大きく変わるという理不尽さを生みます。しかも、格差が広がれば広がるほど、企業内での「公平感」も失われ、働きがいや忠誠心も薄れていきます。
4. 経済格差と横並び意識の崩壊
かつての日本は「みんな一緒」が当たり前でした。新卒一括採用、終身雇用、年功序列。いい大学に入り、大企業に就職すれば一生安泰という暗黙の“社会契約”が機能していたのです。
しかし現在、その前提は音を立てて崩れています。給与・待遇は個別企業ごとにバラつき、雇用は流動化。副業・転職も一般化するなかで、「自分の人生は自分で選ぶ」という意識が求められるようになりました。
言い換えれば、「横並び」の時代から、「選択と競争」の時代へのシフトです。
5. 若年層の雇用悪化と低賃金業務の増加
大学を出ても、安定した職に就けない若者は増えています。特に「高度な教育を受けた人材」ほど、その期待と現実のギャップに苦しみます。
一方で、低賃金のサービス業や契約・派遣労働は増加傾向。物流、介護、飲食など人手不足の現場に、若い人が使い捨てのように投入される構造が広がっています。
これは一時的な経済変動ではなく、構造的な問題。労働の価値が分断されていく中で、「どの職に就くか」がそのまま人生全体の選択肢を左右するリスクが高まっています。
6. 世代間格差の広がり
日本では、バブル期に就職した団塊ジュニア世代と、現在20代の若年層とでは、資産形成や雇用の安定性において大きな差があります。
団塊世代の多くは持ち家があり、退職金や年金にも一定の保障がありますが、若年世代は「賃貸暮らし・非正規雇用・老後不安」が現実味を帯びています。
インフレはこの世代間の格差をさらに拡大します。物価が上がっても年金収入は守られがちなのに、現役世代の給与は上がらない。その矛盾が「若者ほど損をする社会」という不公平感につながっています。
7. 自分の価値観が問われる時代へ
──競争か、共創か
こうした社会の中で、私たちは何を選ぶべきでしょうか?「企業に依存して年功序列の枠内で生きる」道は、今や安定でも安心でもありません。
だからこそ、自分なりの価値観を持ち、「競争」だけでなく「共創」という選択肢にも目を向けることが重要です。
- 自分の得意を生かして複業する
- 小さなコミュニティでの仕事に価値を見出す
- 共感でつながるチームとプロジェクトを立ち上げる
- NPOやスタートアップ、地方創生に関わる
こうした「企業外の選択肢」は、まだ収入が少ないかもしれません。でも、「誰と、どんな目的で働くか」を自分で決められることこそが、これからの時代の“本当の価値”かもしれません。
おわりに:人生を“委ねる”のではなく“選ぶ”
インフレの時代、そして企業が万能ではなくなった今、私たちは「どこで働くか」ではなく、「どう生きたいか」を軸に選択をしていくべきです。
社会は厳しい。それは確かです。でも、自分の価値観を磨き、誰かと共創していくことで、“小さな豊かさ”を積み重ねることはできます。
「競争するだけの人生」ではなく、「共に創りあう人生」を、あなたは選びますか?




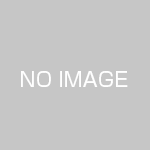


 PAGE TOP
PAGE TOP
この記事へのコメントはありません。