私たちが「成長」と聞いたとき、まず思い浮かぶのは売上や利益、GDPといった数字ではないでしょうか。こうした“量”の拡大はわかりやすく、評価もしやすいからです。日本も戦後から長らく、この「量的成長」を追い求めてきました。
でも成長にはもうひとつ、「質」の側面があります。上下水道や電気がどれくらい普及しているか、教育や医療の水準、あるいは日々受けているサービスの快適さなどです。質は数字にしにくいからこそ、見過ごされやすいのです。
戦後日本の「量」偏重
日本は戦後復興の中で、とにかくモノを安くたくさん作ることが重要でした。そのおかげで生活水準は一気に向上しましたが、「サービスは無料でついてくるもの」「機能を増やせば価値が上がる」という考えが社会に根づいてしまいました。結果として、目に見えにくい質――人の時間や知識、サービスの快適さ――にはお金を払わない文化が広がったのです。
質を評価できない社会の副作用
こうした価値観は、イノベーションを支える力を弱めました。もちろん、日本はかつて家電やゲーム、車など世界を驚かせる製品を次々と生み出しました。しかし90年代以降、規制や資金面の問題に加えて「質への評価不足」もあって、新しい挑戦に投資が集まりにくくなった。結果、成長が頭打ちになった側面があります。
労働市場にも同じことが言えます。世界で評価される研究者や大ヒットゲームを生むクリエイターでさえ、日本では報酬が海外に比べてかなり低い。質を正しく評価しないと、人材は育たず、海外に流出してしまいます。
これから必要なのは「質」へのシフト
日本がこれから成長していくためには、「どれだけ大きな数字を出せたか」だけでなく、「どれだけ質の高い成果を生み出せたか」を評価する意識が欠かせません。たとえば、
- サービスの快適さに正当な料金を支払う
- 研究や創造性を成果として認める
- 幸福度や生活の充実感を経済指標と並べて考える
こうした意識が社会全体に広がっていくことが、日本の持続的な成長につながるはずです。
おわりに
量を追い求める時代は確かに成果をもたらしました。でも今必要なのは、「質をどう評価し、どう対価を払うか」を考えることです。あなたの仕事でも、数字に現れない質的な部分が、実は大きな価値を持っているのではないでしょうか。そこに目を向けられるかどうかが、次の時代の成長のカギになるはずです。



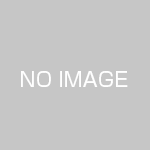




 PAGE TOP
PAGE TOP
この記事へのコメントはありません。