近年、AI(人工知能)の進化に伴い、多くの職種がAIに取って代わられる可能性が指摘されています。例えば、一般事務、銀行員、スーパーやコンビニの店員、タクシー運転手など、定型的な作業やパターン化された業務は、AIによる自動化が進むと予想されています。
しかし、これらの議論は職種に焦点を当てることが多く、仕事の本質を見落としている可能性があります。同じ石を積む作業でも、その作業内容に注目するのか、目的や成果、意義に注目するのかで、取り組み方や価値が大きく変わるという寓話があります。このように、仕事には効率や手順、コストなどの「サイエンス」な部分と、意義や成果などの「アート」な部分が存在します。
AIは、膨大なデータの処理や分析、定型的な業務の自動化など、サイエンスの領域で大きな力を発揮します。例えば、AIを活用することで、ルーチンワークやデータ入力などの繰り返しの作業を自動化し、作業時間を大幅に短縮することが可能です。 これにより、人間はより創造的で意義のあるアートの部分に注力できるようになります。
これからの若い世代が仕事に取り組む際、自分の人生と向き合い、いかに人生のアートな部分に注力するかで、人生の満足度が大きく変わってくるでしょう。AIがサイエンスの部分を担うことで、人間は創造性や共感、倫理観といった人間ならではの能力を発揮しやすくなります。
また、人生100年時代と呼ばれる現代、少子高齢化が進む社会においては、中高年世代も世代間で仕事を奪い合うのではなく、日常のアートな部分に着目し、AIを上手く活用しながら人生の質を追求することが求められます。AIの導入により、業務の効率化やコスト削減が可能となり、単純作業から解放されることで、より充実した人生を送ることができるでしょう。
これからの日本社会では、人生の効率(サイエンス)だけでなく、人生の質(アート)に取り組むことが重要な時期に来ています。AIを活用して業務を効率化し、人間はより創造的で意義のある活動に専念することで、個々人の満足度や社会全体の幸福度を高めることができるでしょう。
AIの進化は、私たちの仕事や生活に大きな変革をもたらしています。その変化を前向きに捉え、AIと共存しながら人間らしい価値を追求することが、これからの時代に求められる姿勢ではないでしょうか。




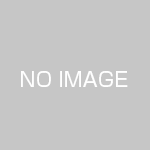

 PAGE TOP
PAGE TOP
この記事へのコメントはありません。