最近、社会は「正義(正解)」をめぐる分断と対立の流れにさまよっているように感じます。SNSやニュースサイトの記事を見ると、そこに潜むのは「自分の正義(正解)」を一方的に主張する声です。立場や背景に触れることなく、ただただ相手を否定する。それは、人々が「正義(正解)」の名の下で狭量な歩みを進めていることを意味しているのではないでしょうか。例えば、「誤った正義は、もっとも悪しい不正である」と言ったベンジャミンの言葉を思い起させます。
正義の知識は、常に個人の見方や信念によって決定されますが、それが社会的な相互理解を損ねることが多々あります。個人の正義が、結局は論議や解決の場を失う原因になっている事例も少なくありません。
社会に出ると「正解」が存在する場面は少なく、そこに存在するのは、「その場」「その時」「その人」にとって最適な選択をする力です。人はそれぞれの正義を持ちますが、いつでもそれが大きな明確な「最適」に繋がるわけではないのです。
プロアスリートを例にすると、その日の気温や体調に依ってプレーの質や強度を変えることが求められます。チームプレーであれば、チームの状態も考慮しなければなりません。これは「正解」を追い求めるのではなく、「最適な行動」を選択する力です。
商品企画においても、実は似たロジックが適用されます。プロダクトを設計する際、完璧な機能や正解を目指すより、使用者の状況やニーズに合わせた「最適」な機能を提供することが重要となります。コスパやタイパを考慮したデザインは、実際に人々の心を揺り動かします。これもまた「正義(正解)」ではなく「最適」の発想です。
正義(正解)を追求するあまり、他人の視点や状況を無視してしまうことは、ある意味「狭量さ」を生む原因になります。アイザック・ベルは「単にことを決定するのではなく、結果が元になって考えることが不可欠である」と言いました。これは、ある状況で最適な決定をするために、これまでのプロセスを見返り、相手の視点に立つことです。
社会も組織も多様な人間の集まりであり、画一化された工業製品の集まりではありません。多くの人が集まる以上、多くの考え方、置かれた環境がありその中でより多くの人が納得できるルールや決まり、行動規範などを設定し、常にアップデートすることが求められるのです。
実際に科学技術の発展や思想の深化により、我々の常識や社会体制、法律なども常にアップデートされています。
これの視点をもって、私たちは「正解(正解)」の単一性に固執せず、もっと広い視点で「正義(正解)」の意味を捉え直す必要があるのです。「正義(正解)」は時に社会の同意と構造によって変化します。ゆえに、決して一般化はできません。それどころか、一方の視点から見るとその行為が不正に見える場合もあります。
私たちは「正義」という観念を、個人のモラルや信念に基づいたものではなく、個別の状況に対応した「最適」を追う機能として再解釈する必要があるのではないでしょうか。





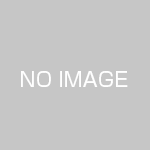


 PAGE TOP
PAGE TOP
この記事へのコメントはありません。